いよいよ大晦日です。
日没は、札幌が16時9分、東京16時37分、福岡17時20分、沖縄17時48分。
日本列島は細長い形ですので、歳神様もお忙しいようで。
※国立天文台 暦計算室データより
さて、今年最後の記事は、木の国と歳神様のご利益について、お話させていただきます。
まずはこちらから。
☆日本神話と紀伊国と
・紀伊国
和歌山県と三重県にまたがる地域を、紀伊国(きいのくに)と言いますね。
これは元々、木の国だったんです。
あの辺りは本当に森が深い、今でもです。
雨も多いし、水もきれい。
熊野地方の川なんて、水が流れているのに水が見えない感じで、こんな場所が日本にあるんだと感動したものです。
ではなぜ木の国を「きいのくに」と発音したのかと言うと、方言らしいですね。
あちらの地方では、「き」を「きぃ」と発音するので、きぃのくに、、、きいのくに。
それに漢字をあてて、紀伊國、、、紀伊国。
さてその紀伊国に熊野神社がありますね、熊野三山。
そこの本宮の主催神は、スサノオの尊。
・スサノオノミコト(素戔嗚尊)
日本神話には、三貴神という神様がおわします。
ご兄弟なんですが。
アマテラス(太陽神)
ツクヨミ(月神)
そしてスサノヲ。
(※スサノヲは、歴史的仮名遣い。いまではスサノオ。)
このスサノヲ(素戔嗚・スサノオ)の尊が、良く分らない。
海の波打ち際を治めるとか、いや台風の神だとか。
ヤマタノオロチを退治した英雄神でもあれば、世界に暗黒をもたらした超破壊神でもある訳です。
かなり高名でありながら、良く分らない神様なんです。
そんなスサノオですが、さらにややこしい事に樹木神と言う一面があるのですよね。
木がないと、これからこの国に生まれてくる多くの子たちが困るだろうと、ご自分の体毛をブチブチ抜いて、大地に刺してそれが森に変化したというのです。
そしてスサノオの子たちに命じて、全国に植樹をさせて行ったというんですね。
そのスサノオが、紀伊國に一大勢力を誇っていた熊野一族の総本社、熊野本宮大社の主催神として鎮座されているのです。
まさに、木の国でありますね。
さらに申しますと、このスサノオ。
出雲を治めた後、黄泉の国(死者の国)をに治まることになります。
この黄泉の国を別名、根之堅洲国。
根の国とも呼ばれます。
そう。
樹木神が、最後は根の国で鎮まるんですね。
あとひとつ!
日本で最初に和歌を詠んだのが、スサノオと言われています。
八雲立つ、、、のあの歌ですね、出雲を詠った。
そこで。
樹木神の性格もあるスサノオが和歌の始祖という訳ですから、その始祖を主催神にすえる熊野三山の影響力のあるこの地方を、和歌山と称したのかなと私は思います。
・スサノオ余談
日本神話の三貴神ですが、アマテラスとツクヨミはまだ性格がハッキリしています。
伊勢神宮の主催神として、最高神の位置に付く太陽神アマテラス(天照)オオミカミ。
ツクヨミは月読で、そう記述は多くなくひっそりとしています。
そう、昼と夜。
こうしてみてもスサノオだけ浮くんですね。
もしかして。
アマテラスとツクヨミは弥生以降の農耕神で、今の国家を作った渡来神なのかもしれませんね。
そうすると、自然崇拝をしていた縄文神がスサノオではないかとも私は考えています。
何を考えているのかわからないスサノオ。
アマテラスと和合しようとして、戦いになり、それに敗れて追放されつつ、英雄となるスサノオ。
森を大切にし、育てようと努めたスサノオ。
いやいや、こういう話は好きなのでついつい長くなりましたね、すみません。
・紀伊国屋書店
ここまで来たら、余談ついでにこちらも。
紀伊国屋書店と言う本屋さんがあるでしょう。
なぜに紀伊国屋なのか。
これは創業者のご先祖が、紀伊徳川藩江戸屋敷に勤めており商売もすることになった。
その時に、出身地の紀伊國を屋号としたのだそうです。
面白いことに、その商売と言うのは本屋ではなく材木商だったそうですよ。
さすが木の国、スサノオゆかりの地ですね。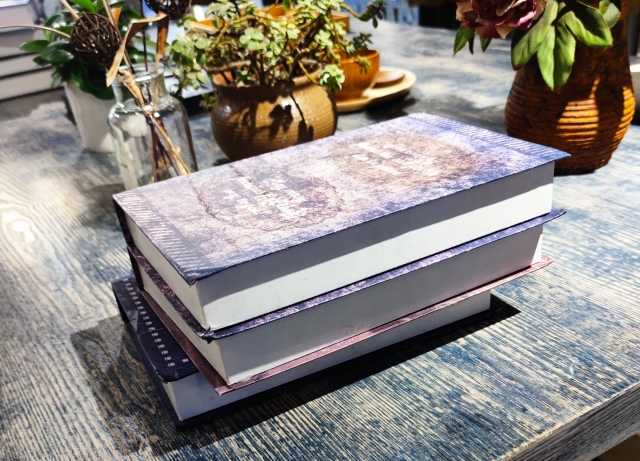
☆歳神様のご利益
さて本題。
すみません、いつものように前置きが長すぎました。
ではこれまでに申し上げてきた歳神様ですが、お迎えするとどういうご利益があるかと言う話です。
一般に言われているのが、以下の通り。
・長寿
・無病息災
・家内安全
・五穀豊穣
・商売繁盛
つまり、新しい一年の幸福と健康と幸運をまとめて運んできてくださるのだそうです。
しかし、どこにでも歳神様がやって見えるのかと申しますと、そうでもないようです。
条件があるんですね。
それがこれまで申し上げてきた、松迎えや大掃除などを決められた期日までに行い、鏡餅などの依代を正しく飾る事なんだそうです。
これを実際やってみますと、実に清々しいんですね。
これまで、仕事や子育てに忙しいからと、大掃除も鏡餅も適当にやっていたことが多かったんですが、こういう決まりをきちんとやるようにしてからは、気持ちがすっと洗われるようなんです。
やはりこうして歳神様迎えの一連の行事を考えながらやっていますと、どうも縄文時代からの日本人の自然観に直接触れているような気がしてくるんですね。
もしかするとこの気持ちは、日本人が日本人であるために、とても大切なものなのかもしれないと思う大晦日です。
では、今年八月より立ち上げたこの緑の命。
お付き合いいただきましてありがとうございました。
皆さま、来年もどうぞよろしくお願い致します🎍



